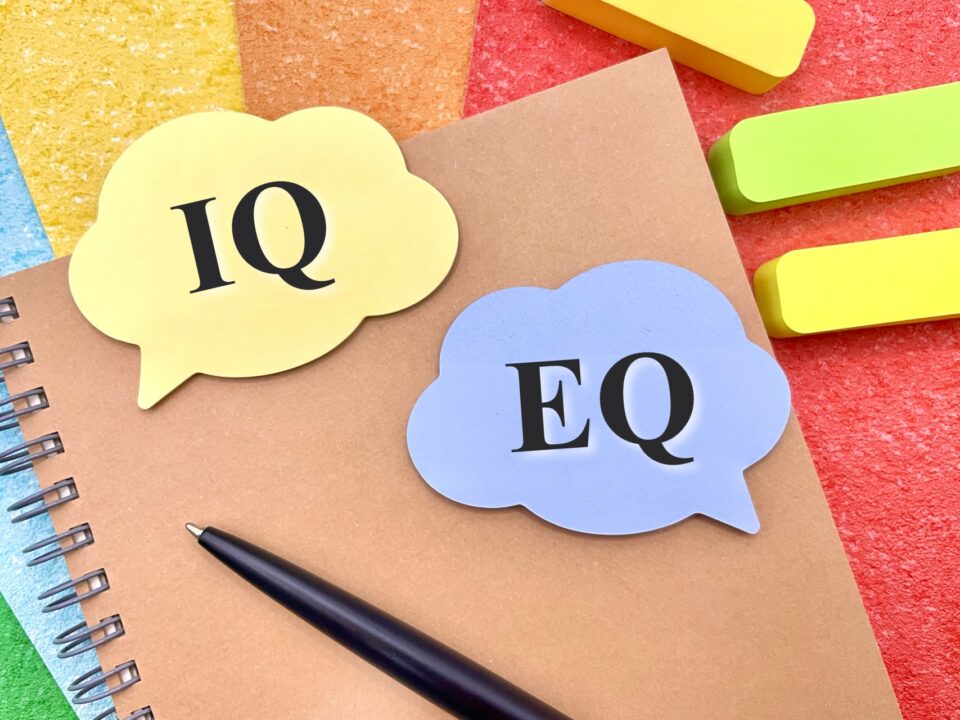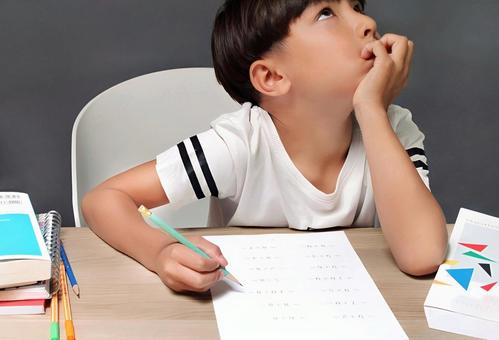子どもの発達障害とは?特徴や相談方法について解説!
2025-01-15
職場のコミュニケーション改善するリーダーシップ7選【前編】
2025-07-08あなたの職場で「心理的安全性」は確保されていますか?
例えば、職場の会議やプロジェクトでメンバーがミスを恐れて沈黙してしまい、自由に発言できずにいる状況に心当たりはありませんか?もし職場の心理的安全性が欠けている状態だと、チーム内のコミュニケーションは停滞し、創造性や生産性も低下します。実は、これは多くの企業で見られる深刻な課題です。
この記事を読み心理的安全性を確保する方法を取り入れれば、メンバーは安心して意見を共有できるようになり、活発な意見交換や革新的なアイデアが生まれる環境をつくることができます。その結果として、組織全体のパフォーマンスが劇的に向上します。
一方で、この問題を放置すると、優秀な人材ほど他の組織へと流出してしまうリスクが高まります。これは短期的な成果だけでなく、企業の将来的な競争力にまで悪影響を与える恐れがあります。
この記事では、心理的安全性の定義やメリット、職場に心理的安全性を浸透させるためのリーダーの役割について詳しく解説します。また、実際に心理的安全性を導入し成功を収めた企業事例を交えて、具体的なステップをご紹介します。

この記事でわかること
- 職場のコミュニケーション改善の具体策を学べる
- チームの生産性と意欲を向上させるヒントを得られる
- リーダーとして心理的安全性を高める行動がわかる
この記事で解説する内容
- 心理的安全性とは?
- 職場で心理的安全性を導入する具体的なメリット
- 心理的安全性を構築するためにリーダーが果たすべき役割
- 職場で心理的安全性を築くための具体的方法
- 成功事例の紹介と分析
この記事を書いた人
公認心理師・ブレインジムインストラクターの吉尾 香奈子が執筆・監修。
元小中学校教員として10年間で1000人以上の子どもを指導。現在は教育委員会巡回相談員、心理検査員、子どもの発達に関するNPO副代表理事などを務める。教育・心理・経営の専門知識と現場経験に基づき、理論と実践のバランスを重視。心理学や海外の教育メソッドなどの専門知識を、今日から教育現場で使える知識として提供。「学び方」「働き方」「生き方」の多様性を尊重し、一人ひとりが輝ける社会を目指している。
この記事では、Googleが行った研究「プロジェクト・アリストテレス」をはじめ、専門的な研究や事例をご紹介しています。まなびかたlab代表の吉尾自身の組織開発経験を交えた、職場で実践できる実用的な内容となっていますので、ぜひご参考になさってください。
目次
心理的安全性とは何か?職場に与える影響を解説

心理的安全性の定義とGoogleの研究「プロジェクト・アリストテレス」の発見
心理的安全性とは、職場において「チームメンバーが失敗を恐れずに自由に意見を述べ、疑問や問題点を気兼ねなく指摘できる環境」のことです。
近年、この概念が注目されるようになったきっかけは、Googleが行った「プロジェクト・アリストテレス」という研究でした。この研究では、高いパフォーマンスを発揮するチームには特定の共通要素が存在することが明らかになりました。驚くべきことに、チームメンバーの能力やスキルよりも、「心理的安全性が高いこと」が、チームの成功を左右する最も重要な要素だと判明したのです。
心理的安全性が高い職場では、「無知だと思われる」「失敗を責められる」「意見を否定される」といった恐れがなく、メンバーが安心して意見やアイデアを共有できます。その結果、職場のコミュニケーションが活性化し、組織全体のパフォーマンス向上に大きく貢献するのです。
心理的安全性が高い職場と低い職場の違いとは?
心理的安全性が高い職場と低い職場では、コミュニケーションの取り方やチームのパフォーマンスに明確な違いがあります。
| 心理的安全性が高い職場 | 心理的安全性が低い職場 |
|---|---|
| 自由に意見を述べられる | 発言にためらいが生じる |
| ミスを成長機会と捉える | ミスを隠そうとする |
| メンバー間の信頼関係が強い | メンバー間の連携が弱い |
| 建設的なフィードバックがある | 批判的な指摘が多い |
心理的安全性が低い職場では、メンバーは自己防衛的になり、新しいアイデアの共有や改善提案を避ける傾向があります。その結果、イノベーションや成長機会が失われるばかりか、優秀な人材の流出という深刻な問題も生じます。
職場で心理的安全性が注目される理由とその重要性
今、心理的安全性が特に注目されている理由は、多くの企業がコミュニケーション不全による生産性の低下や、優秀な人材の流出に悩まされているからです。働き方改革やリモートワークが普及した現在、職場での意思疎通が難しくなり、心理的安全性を高めることが組織運営の最優先課題になっています。
心理的安全性が高まることで、職場では下記のような良循環が生まれます。
- メンバーが安心して自由に発言する
- 活発な議論やアイデアの共有が行われる
- 問題点や課題が早期に発見され、迅速な改善が図れる
- チーム全体のモチベーションが向上し、生産性が高まる
逆に言えば、心理的安全性を欠いたままでは組織の生産性は下がり、離職率も高まることになります。
職場に心理的安全性を導入する具体的なメリット

職場に心理的安全性を導入すると、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか?
ここでは、実際の研究や事例をもとに詳しくご紹介します。
メリット①:コミュニケーションが活性化し、創造性が向上する
心理的安全性がある職場では、メンバーが失敗や否定を恐れず自由に意見を出し合えるため、自然とコミュニケーションが活発になります。例えば、新しいアイデアや斬新な解決策が求められるプロジェクトにおいても、メンバーが臆することなく意見を交換できるため、革新的な発想が生まれやすくなります。
Googleの研究でも、心理的安全性が高いチームほど新たなアイデアを迅速に共有し、問題解決のスピードが速いことが明らかになっています。
メリット②:メンバーのモチベーションと生産性の向上
心理的安全性が高い職場では、メンバーは自分の意見やアイデアが受け入れられることを実感でき、仕事に対するやりがいやモチベーションが向上します。その結果、個々の生産性が高まり、チーム全体としての成果も向上する傾向にあります。
また、心理的安全性が確保されている職場では、失敗を恐れず挑戦する姿勢が評価されるため、従業員の積極性や自発性も高まり、結果的に生産性が大幅に改善します。
メリット③:離職率の低下と人材定着率の向上
メンバーが安心して働ける環境が整うことで、企業に対する帰属意識が高まり、結果的に離職率が大きく低下します。これは特に人材不足が深刻な現代社会において極めて重要です。
心理的安全性が高い組織では、従業員が自分の意見や価値観が尊重されていると感じられるため、会社への信頼感や忠誠心が高まり、人材の定着が促進されます。
メリット④:具体的なデータと成功事例から見る効果
心理的安全性の効果は、世界的に著名な企業だけでなく、日本国内の企業においても確認されています。例えば、日本のあるIT企業では、心理的安全性の導入後、従業員の意識調査で「職場満足度」が大幅に改善し、チームの生産性も前年比で約30%向上したという結果が報告されています。
また、別の製造業企業でも、心理的安全性の導入により、コミュニケーション不全による作業ミスが減少し、品質改善に直結した成功事例があります。
これらの事例からも、心理的安全性が職場にもたらすメリットが非常に明確であることがわかります。
心理的安全性を構築するためにリーダーが果たすべき役割

職場で心理的安全性を高めるためには、リーダーやマネージャーの役割が非常に重要です。ここでは、チームの心理的安全性を向上させるために、リーダーは何をすべきか具体的にご紹介します。
リーダーは「管理者」ではなく「支援者」であるべき理由
心理的安全性を高めるためにリーダーがまず理解すべきことは、「管理者」ではなく「支援者」であることです。メンバーを「管理」するという意識を捨て、メンバーが最高のパフォーマンスを発揮できるよう「支援」することを役割の中心に据えるべきです。
具体的には、業務プロセスを管理しながらも、「困った時はいつでも相談してほしい」「失敗を恐れず挑戦を応援する」というメッセージを常に発信し、メンバーを心理的に支える役割を担います。
自己開示とオープンなコミュニケーションが職場環境を変える
リーダーが心理的安全性を構築する際に特に効果的なのが、「自己開示」です。リーダー自身が自分の得意なことや苦手なこと、過去の失敗体験をオープンに話すことで、メンバーは安心して自分自身も素直に表現できるようになります。
私も過去に、リーダーとして自らの失敗経験や苦手分野をチームに正直に伝えることで、チーム内の信頼感が劇的に高まったという経験があります。結果としてチームの連携力が向上し、業務パフォーマンスも大幅に改善されました。
アンコンシャスバイアスを防ぐためのリーダーの行動指針
アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)は、心理的安全性を大きく損ないます。リーダーが知らず知らずのうちに特定のメンバーに偏った評価やコミュニケーションをしてしまうと、職場全体の心理的安全性は急激に低下します。
そのため、リーダーは公平かつ透明な態度を常に意識する必要があります。例えば、定期的にメンバーとの1on1ミーティングを実施し、全員と平等にコミュニケーションを取り、公正な評価を心がけることが重要です。
心理的安全性を高めるリーダーシップとは?
私自身が組織のリーダーとして心理的安全性の向上に取り組んだ際、以下のような具体的な工夫を実践しました。
- 会議の冒頭で、メンバー全員に最近あった良いことや挑戦したことを話してもらう「チェックイン」の時間を設ける。
- ミスがあったとき、責めるのではなく、ミスから学んだことや改善策を共有し、チーム全体の成長に繋げる。
- 自ら進んで自分の弱みや失敗を語り、メンバーが安心して自己開示できる空気を作る。
これらの具体的なアクションにより、メンバーは自分の意見や気持ちを隠さず伝えられるようになり、組織全体の生産性とモチベーションが向上しました。
職場で心理的安全性を築くために私が実践している具体的方法

ここでは、職場の心理的安全性を高めるために、私自身が実際に実践している具体的な方法についてお伝えしたいと思います。私がこれまで取り組んできた中で、特に効果が高かった手法を厳選しましたので、ぜひあなたの職場でも試してみてください。
「会話」ではなく「対話」を職場に取り入れる
私は普段、メンバーとのコミュニケーションを単なる情報伝達の「会話」で終わらせず、お互いが深く理解し合える「対話」に変えるよう意識しています。
具体的には、会議やミーティングの場で、メンバーの発言に対して「どうしてそう感じたの?」「そのアイデアが生まれた背景を教えてくれる?」といった質問を積極的に投げかけています。こうした問いかけを繰り返すうちに、メンバーも自分の考えを安心して伝えてくれるようになりました。
メンバーが前向きになれるフィードバックの与え方
以前は私自身、フィードバックをするときに、つい改善点ばかり伝えてしまい、相手の気持ちを傷つけてしまうこともありました。そこで意識的に取り入れたのが、「成長を促すフィードバック」です。
フィードバックの手順としては、
- メンバーの努力や良かった点を認めて伝える
- 改善すべきポイントを具体的かつ客観的に伝える
- 一緒に具体的な解決策を考える
という流れを実践しています。この方法に変えたところ、メンバーが前向きに改善を受け入れ、積極的に行動を変えてくれるようになりました。
定期的な1on1ミーティングと、日常の雑談を大切にする
私が心理的安全性を高めるために最も効果的だと感じていることは、メンバーとの定期的な「1on1ミーティング」と、気軽な「雑談」です。
1on1ミーティングでは、業務の進捗確認だけでなく、「最近困っていることはある?」「仕事以外で気になっていることは?」といった話題を自然に引き出すようにしています。また、私は仕事の合間にも雑談をよくするのですが、趣味の話やちょっとした出来事など、プライベートな話を交えることで、メンバーとの距離感がグッと縮まります。
こうした日常の積み重ねが、メンバーとの信頼関係を築き、職場の心理的安全性の土台になっています。
悪い知らせをポジティブな成長機会として共有する
最後に私が大切にしているのが、職場で何かトラブルや問題が起きた時の対応方法です。以前はトラブルが起きるとつい犯人探しのような雰囲気になってしまうこともありましたが、それでは誰も安心してミスを報告できません。
そこで、私は問題が起きた時にはまず「この経験から何が学べるか」を考え、メンバー全員で解決策を共有する場を設けるようにしました。「失敗=責任追及」ではなく、「失敗=学びのチャンス」という空気を作ることで、メンバーは次第に問題を積極的に報告し、自ら改善策を提案するようになりました。
心理的安全性を導入して成功した企業の具体的な事例

ここまで心理的安全性のメリットや具体的な取り組みについてお伝えしてきましたが、「実際に心理的安全性を取り入れて成功した企業はどんなことをやっているの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
そこでここからは、心理的安全性を導入し、職場環境が劇的に改善された具体的な成功事例を2つご紹介します。私自身も参考にしたこれらの事例が、あなたの職場環境改善のヒントになれば嬉しいです。
事例① Googleの「プロジェクト・アリストテレス」によるチーム改革
最も有名な心理的安全性の成功事例は、やはりGoogleが行った「プロジェクト・アリストテレス」でしょう。このプロジェクトは、世界中の優秀なチームを調査し、高い成果をあげるチームに共通する要素を明らかにした研究です。
この研究の結果、チームメンバーの学歴や能力ではなく、心理的安全性がチームのパフォーマンスに最も大きく影響することが判明しました。
Googleはこの結果を受けて、以下のような取り組みを実践しました。
- リーダーが積極的に自己開示を行い、メンバーとの信頼関係を強化した。
- 意見が対立しても相手を否定せず、必ず「なぜそう思うのか」を掘り下げる議論を推奨した。
- ミスを成長の機会と位置付け、「ポストモーテム(事後検証)」と呼ばれるミーティングを実施して、再発防止と学習を促した。
こうした取り組みの結果、チームのコミュニケーションは活性化し、問題解決スピードが格段に向上。革新的なサービスやアイデアが次々と生まれるようになったのです。
事例② 国内IT企業のリーダーシップ変革による業績向上
日本国内でも、心理的安全性の導入に成功した企業事例があります。ある中堅IT企業では、社員間のコミュニケーション不足や離職率の増加に悩んでいました。その解決策として心理的安全性の考え方を取り入れ、リーダーシップのあり方を大きく見直したのです。
具体的に行ったのは次のようなことでした。
- 全リーダーが「聞き手に徹する姿勢」を身につけ、メンバーが話しやすい雰囲気を作った。
- 定期的に1on1ミーティングを設け、業務の悩みやキャリアの希望について話す機会を作った。
- 「失敗はチーム全体の学習機会」と考え、ミスが起きても責めることなく、改善策をチームで共有した。
この取り組みを実施して半年後、同社の従業員満足度アンケートでは「職場環境への満足度」が前年比で35%も向上。離職率も大幅に低下しました。さらに、チーム内の情報共有や協力がスムーズになったことで、プロジェクトの成功率や品質も大きく改善されたのです。
私自身も、この企業の事例を参考に自分の組織に取り入れ、職場環境が改善されるのを実感しました。
事例から学ぶ職場環境改善のポイント
上記の2つの事例に共通しているのは、心理的安全性を高めるためにリーダーが積極的にコミュニケーション方法を改善し、自らが行動を変えたということです。
職場の心理的安全性を高めるためには、まずリーダー自身が変わること。そして、失敗を恐れず、安心して意見を言える環境を日々の積み重ねで築いていくことが不可欠です。
【まとめ】心理的安全性で職場環境を劇的に変えるためのアクションプラン

ここまで心理的安全性の定義やメリット、具体的な導入方法、成功事例をご紹介してきました。
最後に、あなたの職場で心理的安全性を高めるために「今日からすぐに始められるアクションプラン」をまとめてお伝えします。
ぜひ、あなたの組織でも取り入れてみてください。
【Step1】心理的安全性の現状をチェックする
まず、あなたのチームや職場の心理的安全性が現状どの程度なのか、簡単なチェックから始めましょう。私が実際に使っている質問項目は次のようなものです。
- メンバーは気兼ねなく意見を言えているか?
- ミスや失敗を隠さず報告できる環境か?
- チーム内で相互に建設的なフィードバックが行われているか?
- メンバー同士、あるいはリーダーとメンバーの間に信頼関係があるか?
これらの質問をチームで共有し、オープンに話し合ってみてください。これだけで職場の状況を客観的に把握できます。
【Step2】リーダー自身が自己開示を始める
心理的安全性を高めるには、リーダー自身が自己開示を率先して行うことが非常に効果的です。
私自身も、最初は少し抵抗がありましたが、意識的に自分の失敗談や苦手なことをメンバーに伝えるようにしました。その結果、驚くほどチーム内のコミュニケーションが活性化しました。
自己開示の例としては、
- 過去に自分が経験した失敗や、その時にどう対応したか
- 最近感じている職場での悩みや課題
- 自分が今取り組んでいる改善点や成長目標
などがあります。まずは小さなことから始めるのがポイントです。
【Step3】メンバーとの「対話」の時間を作る
定期的に、メンバーが自由に意見や疑問を話せる「対話」の時間を設けましょう。
私の場合、週に1回30分〜1時間程度、業務のことだけでなくメンバーのプライベートや気持ちについても話せる場を作っています。
その際に大切なのは、「否定せず、じっくりと話を聞く」姿勢を示すことです。
私自身、聞き役に徹することで、メンバーが安心して自分の考えや悩みを話してくれるようになりました。
【Step4】ポジティブなフィードバック文化を作る
フィードバックの文化を根付かせるには、最初はリーダーが積極的に「良かった点」や「頑張り」を伝えることから始めます。
私も初めは、「メンバーが調子に乗ってしまうのでは?」と不安でしたが、実際はその逆でした。
メンバーはより積極的にチャレンジし、自発的に改善を行うようになったのです。
慣れてきたら、「改善すべき点」も前向きな言葉で伝えることを意識しましょう。
【Step5】「ミス=学習のチャンス」という考えを徹底する
最後に、心理的安全性を確実に定着させるには、「ミスは学習のチャンスである」という価値観を徹底することが欠かせません。
トラブルが起きた際は、メンバー個人を責めず、必ずチーム全体の学習機会に変えましょう。
私はトラブルが起きるたびに、「次はどう改善できるか」をメンバー全員で考えるようにしています。その結果、メンバーが失敗を恐れずチャレンジする文化が定着しました。
最後に
職場の心理的安全性は、一夜にして築かれるものではありません。
日々の小さな積み重ねが、やがて大きな変化を生み出します。
ぜひ今日から、このアクションプランのうち一つでもいいので、始めてみてください。
私たち『まなびかたlab』でも、心理的安全性を高めるサポートを随時行っていますので、
お困りの際はお気軽にご相談ください。
あなたの職場が、心理的安全性の高い、生産的で幸福度の高いチームに変わることを心から願っています。